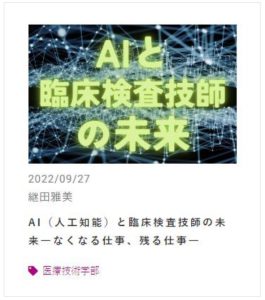タスクシフト/シェアで広がる臨床検査技師の活躍の場
みなさん、こんにちは!
新潟薬科大学の継田です。
先日YAKUDAI WALKにて「AIと臨床検査技師」についてのお話をしました。
今回はその続きとして「いずれこんな仕事も臨床検査技師に任される!」というお話をしたいと思います。
日本臨床衛生検査技師会では、「タスク・シフト/シェア」に力を入れています。
これは、医師にしか行えなかった業務の一部を他の職種に分担する仕組みのことで、臨床検査技師にも分担が要請されています。
これは厚生労働省による研修を受ければ出来るようになるのですが、その仕事とはどんなものなのかいくつかご紹介したいと思います。
タスク・シフト/シェア 臨床検査技師が行える新たな仕事
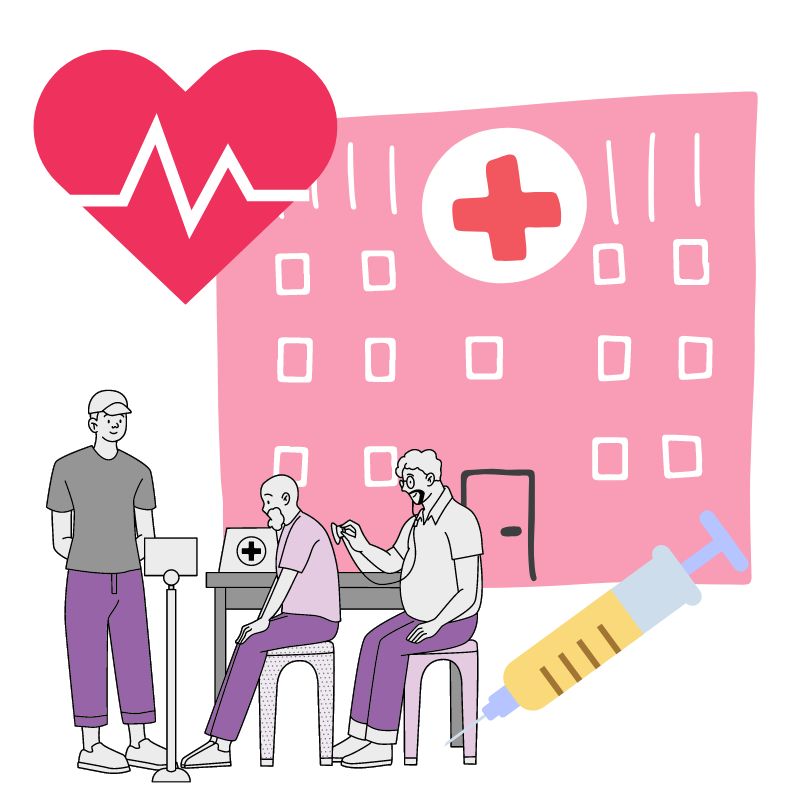
臨床検査技師は採血を行うことは可能ですが静脈路確保ができるようになることで今後は静脈に針を刺して薬物を投与するためのルートをつくることもできます。
これは、注射薬が必要な患者さんのための治療の第一歩です。
医師、看護師に加え、検査技師も行えるようになったことで、医療現場での臨床検査技師の需要はさらに高まります。

皮下グルコース検査とは糖尿病の検査のひとつです。
糖尿病の患者さんはとても多く、治療のために血液中のグルコースの値(血糖値)を測りますが、近年では1点だけの値ではなく、血糖値が急に高くなったり低くなったりしていないか、24時間の変化が重要と言われています。
そのため患者さんのお腹や二の腕などに専用のセンサーを装着することで2週間程度24時間血糖値の変動を追うことができます。
このセンサー装着やレコーダーなどの機器の準備、患者さんへの説明などを臨床検査技師が行えるようになりました。
内視鏡の検査において、医師の指示にしたがって鉗子(かんし)を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取することができようになりました。

これらのタスク・シフト/シェアが広がることで臨床検査技師の活躍できる場面がどんどん広がっていきます。新潟薬科大学で学び臨床検査技師となり共に医療の世界で活躍しませんか。