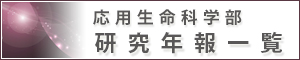応用生命科学部 研究室紹介
応用生命科学はSDGs達成の大きな推進力です。

食品、農業、医療、健康、環境、教育など幅広い産業領域につながっている「生命科学」 は、現代社会には欠かせない、特に「持続可能な開発目標(SDGs)」達成には必要不可欠な学問です。応用生命科学部は学部創設から20年が経ち、SDGsを強力に推進できる学部として成長してきました。本学部は農学系学部であり、応用生命科学科と生命産業ビジネス学科の2学科で構成されています。応用生命科学科は「生命科学」の新しいモノつくり技術(バイオサイエンス)を学び、生命産業ビジネス学科はその技術を活用した新しいビジネス(バイオビジネス)創出を学ぶ学科です。学科横断的に履修できるプログラムがあるため、多様化・複雑化している社会課題への取り組みにおいて、「モノつくり技術からビジネスまでの全てを通して学んだ」経験と自信は間違いなく大きな力になります。また、本学部には10人の異なる潜在能力があったら、10通りの教育法で能力を開花できる教員がいます。ぜひ、本学部で皆さんの能力を開花しましょう。
応用生命科学部長 髙久 洋暁
PICK UP 研究室
食品・発酵工学研究室
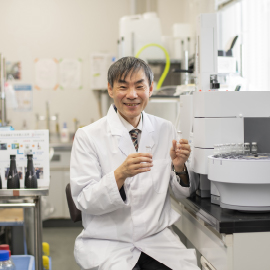
超高圧と発酵技術を駆使して新規食品加工法を開発
海底1万メートルの水圧(1千気圧)を超える「高い圧力(超高圧)」を使った食品加工法や、微生物のはたらきに支えられた発酵技術について研究しています。研究成果を新しい食品の製造・加工技術などに応用しています。
高圧処理日本酒「AWANAMA」を開発しました!
数千気圧の圧力下では熱をかけなくても微生物が死滅します。この現象を日本酒酵母の殺菌に応用することで、生酒の風味を残しつつ保存性の向上した、世界初の高圧処理日本酒の試作品「AWANAMA(あわなま)」を開発しました。国内外の展示会に出展して市場調査を行った結果、若者や外国人にも高い評価を受けることができました。容器として用いたペットボトルも好評で、米国DOW社の Packaging Innovation Awardsで1位に輝きました。
詳細はこちらから
応用微生物・遺伝子工学研究室

バイオテクノロジーは微生物たちの専門領域
SDGsへの取り組みとして「微生物によるモノづくり」技術開発を行っています。その技術として、バイオテクノロジーと情報科学のデジタル技術を融合したスマートセル(スマセル)技術を開発・活用しています。
研究成果が科学誌「Nature」のNature Focal Point 「Focal Point on Synthetic Biology in Japan」特集に掲載され、その成果を通じた学術発展への貢献として新潟日報文化賞を受賞しました!
魚に多く含まれるω3多価不飽和脂肪酸(ω3FA)は栄養価値が高く、世界中で需要が急増していますが、供給が追いついていません。そこで陸上で安定供給ができる油脂酵母でω3FAを合成すべくスマセル技術開発を進め、動脈硬化予防効果を有するω3FAの一種エイコサペンタエン酸を油脂酵母で合成させることに成功しました。
詳細はこちらから
伊藤満敏研究室 食品ビジネス分野

地域貢献をめざす食品ビジネスの創生
食品製造・食品流通・農業関連産業との連携した食品産業の分野の研究を進めています。地域資源を有効利用した食品ビジネスの新たな取り組みが、地域活性化につながるテーマについて研究を行っています。
地域産業を支える企業、行政、研究所および経済団体などと「出口の明確」なテーマについて積極的に連携し「実学一体」の研究方針の実践に努めます。
新潟県の産業別製造品出荷額で、食料品は最も大きな産業で8,000億円を超えます。県内の農業産物を原料に、付加価値の高い加工食品の生産・販売を目指す研究を進めています。本研究室では、健康機能性に富んだ新しい品種のもち大麦「はねうまもち」を利用にした加工食品の製造販売、新潟県で醸造された日本酒を非加熱処理でフレッシュな生酒の状態で、海外に輸出するための新しい日本酒の製造方法及びパッケージ技術の開発などの実績があります。
詳細はこちらから
杉田耕一研究室 農業ビジネス分野

NEW農業を共創して地域社会に貢献しよう!
農業リーディング都市「新潟市」では、農業6次産業化やスマート農業など先端的な取り組みが行われています。農業ビジネス分野では、先端的な農業事業者との共同研究による農産物加工品の開発と共にブランド構築などの販売戦略を加えた新しい農業研究を進めています。
食品開発では、とまと加工食品の開発と消費者嗜好に関する研究を行い、加工食品は「2021フードメッセinにいがた」に出店し、好評を得ることができました。
研究面では、新潟市内のJA農産物直売所などで、生鮮食品や加工食品に関する消費者購買嗜好の調査を行っています。この研究は、農業事業者による6次産業化を成功に導く重要なヒントになると考えています。地域貢献活動では、「小口手摘み製茶法伝承の会」による新津茶の保存活動への参加、及び新津茶の復興に関する研究を行っています。
詳細はこちらから
応用生命科学部 応用生命科学科 研究室一覧
食品科学コース
食の安全を守り、食を通じて健康の増進に貢献
| 研究室 | 教授 | 准教授 | 助教 | 助手 |
|---|---|---|---|---|
| 食品分析学 | 佐藤 眞治 | 桑原 直子(特任) | ||
| 食品機能学 | 松本 均 ※ | |||
| 食品化学 | 能見 祐理 | |||
| 食品安全学 | 西山 宗一郎 | |||
| 食品・発酵工学 | 重松 亨 ※ | |||
| 食品・作物資源利用学 | 大坪 研一(特任) | 中村 澄子(特任) |
バイオテクノロジーコース
生命科学を医薬品や植物育種などバイオテクノロジーに応用する
| 研究室 | 教授 | 准教授 | 助教 | 助手 |
|---|---|---|---|---|
| 応用微生物・遺伝子工学 | 髙久 洋暁 | 佐藤 里佳子(特任) | ||
| 分子微生物学 | 山崎 晴丈 | |||
| 動物細胞工学 | 市川 進一 | |||
| 植物遺伝育種学 | 相井 城太郎 | 中野 絢菜 | ||
| 環境微生物学 | 井口 晃徳 |
生命環境化学コース
環境を測り、守る技術と環境にやさしいものづくり
理科教職コース
理科の「おもしろさ」「楽しさ」を伝える
応用生命科学部 生命産業ビジネス学科 研究室一覧
生命産業ビジネス学科 研究室
食と農の経済学と経営学を学び、人々の暮らしを豊かに
| 研究室等 | 担当分野 | 職名 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 重松 亨 研究室 | 発酵食品ビジネス分野 | 教授 | 重松 亨 |
| 伊藤 満敏 研究室 | 食品ビジネス分野 | 教授 | 伊藤 満敏 |
| 杉田 耕一 研究室 | 農業ビジネス分野 | 教授 | 杉田 耕一 |
| 小瀬 知洋 研究室 | 環境ビジネス分野 | 教授 | 小瀬 知洋 |
| 中道 眞 研究室 | 国際中小ビジネス分野 | 教授 | 中道 眞 |
| 内田 誠吾 研究室 | 経済学・経営学分野 | 准教授 | 内田 誠吾 |
| 松本 均 研究室 | 商品開発分野 | 教授 | 松本 均 |
| 伊藤 美千代 研究室 | 基礎科学ビジネス分野 | 准教授 | 伊藤 美千代 |
| 杉田 耕一/若栗 佳介 研究室 | ビジネスデータサイエンス分野 | 教授 | 杉田 耕一 |
| 助教 | 若栗 佳介 |
研究ユニット
| ユニット名 | 職名 | 氏名 |
|---|---|---|
| 穀物研究ユニット | 特任教授 | 大坪 研一 |
| 准教授 | 相井 城太郎 | |
| 特任准教授 | 中村 澄子 | |
| 発酵醸造研究ユニット | 教授 | 重松 亨 |
| 教授 | 髙久 洋暁 | |
| 准教授 | 井口 晃徳 | |
| 准教授 | 山崎 晴丈 | |
| 食品ビジネスユニット | 教授 | 重松 亨 |
| 教授 | 伊藤 満敏 | |
| 環境微生物機能解析研究ユニット |
准教授(ユニット長) |
井口 晃徳 |
|
准教授 |
山口 利男 | |
|
准教授 |
山崎 晴丈 | |
|
教授 |
重松 亨 |
※ 生命産業ビジネス学科の担当を兼ねる